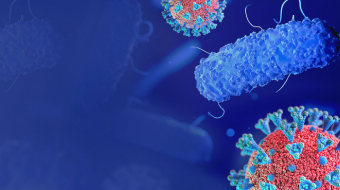研究の『あったらいいな』がきっとみつかる・・・
Promegaは生化学および分子生物学に関連する革新的で価値の高い製品を世界の研究者にお届けするライフサイエンス分野のリーディングカンパニーです。
- NEWS & TOPICS -
お知らせ
-
ようこそRNAの世界へキャンペーン
-
サクッと!細胞アッセイ キャンペーン!!
-
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における指定薬物(いわゆ...
-
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における指定薬物(いわゆ...
-
黄色い大箱ドラゴンキャンペーン